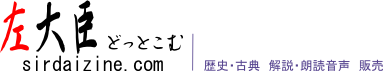父の常陸介拝命
原文
親となりなば、いみじうやむごとなくわが身もなりなむなど、ただゆくへなきことをうち思ひすぐすに、親からうじて、はるかに遠きあづまになりて、
「年ごろは、いつしか思ふやうに近き所になりたらば、まづ胸あくばかりかしづきたてて、率(い)て下りて、海山のけしきをも見せ、それをばさるものにて、わが身よりもたかうもてなしかしづきてみむとこそ思ひつれ。
われも人も宿世(すくせ)のつたなかりければ、ありありてかくはるかなる国になりにたり。幼かりし時、あづまの国に率て下りてだに、心地もいささかあしければ、これをや、この国に見すてて、まどはむとすらむと思ふ。
ひとの国のおそらしきにつけても、わが身ひとつならば、安らかならましを、ところせうひき具して、いはまほしきこともえいはず、せまほしきこともえせずなどあるが、わびしうもるかなと心をくだきしに、今はまいておとなになりにたるを、率て下りて、わが命も知らず、京のうちにてさすらへむは例のこと、あづまの国、田舎人になりてまどはむ、いみじかるべし。
京とても、たのもしう迎へとりてむと思ふ類、親族(しぞく)もなし。さりとて、わづかになりたる国を辞し申すべきにもあらねば、京にとどめて、永き別れにてやみぬべきなり。京にも、さるべきさまにもてなして、とどめむとは思ひよることにもあらず」
と、夜昼嘆かるるを聞く心地、花紅葉の思ひもみな忘れて悲しく、いみじく思ひ嘆かるれど、いかがはせむ。
七月十三日に下る。五日かねては、見むもなかなかなべければ、内にも入らず。まいて、その日は立ち騒ぎて、時なりぬれば、今はとて簾を引き上げて、うち見あはせて涙をほろほろと落して、やがて出でぬるを見送る心地、目もくれまどひてやがて臥されぬるに、とまるをのこの、送りして帰るに、懐紙に、
b思ふこと 心になかふ身なりせば 秋のわかれを ふかく知らまし
とばかり書かかれたるをも、え見やられず、事よろしきときこそ腰折れかかりたることも思ひつづけけれ、ともかくもいふべきかたもおぼえぬままに、
bかけてこそ 思はざりしか この世にて しばしも君に わかるべしとは
いとど人めも見えず、さびしく心ぼそくうちながめつつ、いづこばかりと、明け暮れ思ひやる。道のほども知りにしかば、はるかに恋しく心ぼそきことかぎりなし。明くるより暮るるまで、東(ひんがし)の山ぎはをながめて過ぐす。
語句
■親となりなば 「親とかくなりなば」の意か。 ■ゆくへなきこと あてにならないこと。 ■あづまになりて 孝標は長元五年(1032年)常陸介に任じられた。 ■年ごろ 長年の間。 ■近き所 畿内の国司。 ■胸あくばかり 思う存分。 ■それをばさるものにて それは当然のこととして。 ■ありありて 結局のところ。とどのつまり。最終的に事態が悪くなったニュアンス。 ■あづまの国 上総赴任時のこと。 ■ひとの国 京以外のよその国。 ■ところせう 「所狭く」の音便。場所が狭くなるほどぎゅうぎゅうに密集して。 ■いみじ 悲惨。程度がはなはだしいさま。 ■さるべきさまにもてなして お前にしっかりした結婚相手を見つけてやって。 ■五日かねては 出発五日前となっては。 ■かけて 下に打ち消しの語を伴って「少しも~ない」 ■道のほども知りにしかば 作者はかつて父について上総国に下っているため、あづまへの道のりや日程はほぼ目安がつく。
現代語訳
親がそれなりの地位に立ったら、たいそう高貴なさまに私の身もなるだろうなど、ただあてにならないことを思って長年を過ごしてきたところ、親はかろうじてはるかに遠い常陸国の国司になって、
「長年の間、いつか思っているように都に近い国の国司になったら、まず思う存分お前を大切にして、任国につれ下って、海山の景色をも見せ、それは当然のこととして、自分自身よりも高くお前をもてなして、可愛がってやろうと思っていた。
私もお前も前世の運命がつたいせいで、とうとうこんなはるかな田舎の国に赴任することになってしまった。お前が幼かった時、上総国に連れ下った時さえ、もし私が病気にでもなったら、お前はどうなるだろうと心配だったのに、ましてこんな田舎で私が死んだら、お前を露頭に迷わせることになるだろうと思うのだ。
田舎暮らしの不便さを思うにつけても、わが身一つのことならば、なんとかなるものを、大勢の家族を連れて任地へ下り、言いたいことも言えず、したいこともできずなどあるのが、不憫だと心を砕いていたのだが、今はましてお前は大人になったのだから、任地に連れ下って、私の命もおぼつかない。親が死んだ後、都のうちにて露頭に迷うのはよくある話。まして東国の田舎人として露頭に迷うのは、悲惨だろう。
お前を京に残していっても、お前を迎え入れてくれるしっかりした親類縁者があるわけでもない。そうはいっても、せっかく手に入れた国司の地位を辞退するわけにもいかないので、お前を京に残していって、これが今生の別れともなりそうだ。都でしっかりした結婚相手を見つけてやった後にお前を京に留め置きたいとも思うが、それもおぼつかない」
と、夜昼父がお嘆きになるのを聞く心地といったら、花紅葉を見る悦びもみな忘れて悲しくなり、たいそう思い嘆かれるけれど、どうしたらいいのか。どうにもならない。
七月十七日に父は任地常陸に下ることとなった。出発前五日ともなると、顔をあわせるのもかえって悲しいのに違いない。私の部屋にも入ってこない。まして出発当日はばたばたして、出発の時となれば、さあお別れだということで私の部屋の簾を引き上げて、父と私と顔をあわせて涙をほろほろと落して、すぐに出発するのを見送る心地、目もくれまどいすぐに突っ伏してしまったが、私とともに京に留まることになった下男が、途中まで父の見送りをして帰って来て、懐紙に、
b思ふこと 心になかふ身なりせば 秋のわかれを ふかく知らまし
私が思い通りにできる身であったなら、秋の別れをしみじみとかみしめるのだが、今はその暇もなく、あわただしく出発しなければならない。
とだけ書かれているのを、涙に暮れて私は見ることができない。平穏無事な時であれば下手な歌を書いたことなども思い出され、とにかく何を言うべきかも考え付かないままに、
bかけてこそ 思はざりしか この世にて しばしも君に わかるべしとは
この世で父上とほんの少しでもお別れすることになるなんて、私は少しも思いもしませんでした。
などと私は書いたのだろうか(悲しみのあまり、記憶がはっきりしていない)。
人の訪れも減ってしまい、寂しく心細く物思いに沈みつつ、父は今どへんかしらと、明けても暮れても思いやる。あづまへの道も知っていることであり、はるかに恋しく心細いことは限りも無い。朝から晩まで、東の山際を眺めて過ごした。
前の章「継母の名のりを責める・将来についてのはかない空想」|次の章「太秦参詣・父の便り」