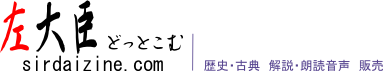尾張から美濃・近江を経て京へ
原文
尾張の国、鳴海の浦を過ぐるに、夕潮ただ満ちに満ちて、今宵宿らむもみ中間(ちゅうげん)に、汐満ちきなば、ここをも過ぎじと、あるかぎり走りまどひ過ぎぬ。
美濃の国なる境に、墨俣といふ渡りして、野上(のがみ)といふ所に着きぬ。そこに遊女(あそび)ども出で来て、夜一夜歌うたふにも、足柄なりし思ひ出でられて、あはれに恋しきことかぎりなし。
雪降りあれまどふに、ものの興もなくて、不破の関、あつみの山など越えて、近江の国おきながといふ人の家に宿りて、四五日あり。
みつさかの山の麓に、夜昼、時雨あられ降りみだれて、日の光もさやかならず、いみじうものむつかし。そこを立ちて、犬上(いぬかみ)、神崎(かんざき)、野洲(やす)、栗太(くるもと)などいふところどころ、なにとなく過ぎぬ。湖のおもてはるばるとして。なで島、竹生島などいふ所の見えたる、いとおもしろし。勢多の橋みなくづれて渡りわづらふ。
粟津にとどまりて、師走の二日、京に入る。暗く行き着くべくと、申の時ばかりに立ちて行けば、関近くなりて、山づらにかりそめなるきりかけといふものしたる上(かみ)より、丈六の仏の、いまだ荒造りにおはするが、顔ばかり見やられたり。
あはれに人はなれて、いづこともなくておはする仏かなとうち見やりて過ぎぬ。ここらの国々を過ぎぬるに、駿河の清見が関と、逢坂の関とばかりはなかりけり。いと暗くなりて三条の宮の西なる所に着きぬ。
語句
■鳴海 名古屋市緑区鳴海町付近。現在は陸地となっているが、当時潮の干満の激しい難所だった。松尾芭蕉は『笈の小文」の旅で鳴海を訪れ「星崎の闇を見よとや啼千鳥」の句を詠んでいる。 ■中間 中途半端。引き返して泊まるにも、鳴海を超えてむこうの宿で泊まるのも、どっちも中途半端の意。 ■美濃の国 岐阜県の南部。 ■墨俣 岐阜県安八(あんぱち)群墨俣町、墨俣川の渡し。尾張と美濃の国境。 ■野上 のがみ。岐阜県不破郡垂井と関ヶ原の中間。遊女が多いことで知られていた。 ■遊女 旅人の宿を訪れ歌や舞によって慰める女。足柄山の章にも登場。 ■不破の関 逢坂の関、鈴鹿の関とともに古代山関の一つ。「秋風や藪も畑も不破の関」(芭蕉) ■あつみの山 所在不明。 ■近江の国 滋賀県。 ■おきなが 滋賀県坂田郡息長(おきなが)村の豪族か? ■みつさかの山 所在不明。 ■ものむつかし うっとうしい。 ■犬上 歌枕。滋賀県犬上郡。 ■神崎 滋賀県八日市市の一部 ■野洲 滋賀県野洲群野洲町。歌枕。 ■栗太 くるもと。大津市内。近江国府があった。 ■なで島 所在不明。 ■竹生島 琵琶湖北部に浮かぶ島。行基建立の弁天堂で知られる。『平家物語』「竹生島」では琵琶の名手平経正が戦勝祈願のために訪れ琵琶の秘曲をかなでる。 ■勢多の橋 琵琶湖が瀬田川に流れ込む河口にかかる橋。古くから交通の要衝で、「勢多橋を制するものは天下を制す」と言われた。壬申の乱や藤原仲麻呂の乱の舞台ともなった。俵藤太秀郷の大ムカデ退治伝説も有名。 ■粟津 大津市東南の湖岸から瀬田にかけての地域。木曽義仲の最期の地として有名。 ■暗く行き着くべくと 旅のやつれが人目につかないよう、暗くなるころを見計らって到着するのは当時の習慣。 ■申の時 午後四時ごろ。 ■関 逢坂の関。近江と山城の境。「これやこの行くも帰るも別れては知るも知らぬも逢坂の関」(百人一首・蝉丸)。 ■山づら 山腹。 ■きりかけ 柱を立て、それに横に板を少しずつずらして打ち付けて、囲いにしたもの。 ■丈六 一丈六尺(約
5メートル)。 ■ここらの国々 たくさんの国々。 ■三条の宮 一条天皇第一皇女修子(しゅうし)内親王。母は定皇后。
現代語訳
尾張の国、鳴海の浦を過ぎていったところ、夕汐がどんどん満ちてきて、今晩泊まるにも、むこうの宿場まで越えてから泊まるにも引き返して泊まるにもどっちつかずの位置に来てしまった。汐が満ちてくれば、ここを通り過ぎることもできなくなると、せいいっぱい走って必死に通り過ぎた。美濃の国との境に、墨俣という渡を渡って、野上という所に着いた。そこに遊女たちが出てきて、一晩中歌うにつけても、足柄山で出会った遊女たちのことが思い出されて、しみじみとなつかしく、どこまでも恋しく思われた。
雪が降りあれまどうので、なんの情緒もないので、不破の関、あつみの山など越えて、近江の国で息長(おきなが)といふ人の家に泊まって、四五日過ごした。
みつさかの山のふもとに、夜も昼も時雨やあられが降りみだれて、日の光もちっともささないので、大変うっとうしい。そこを出発して、犬上・神崎・野洲・栗太などいふ所々、なんとなく通り過ぎた。
琵琶湖の水面をはるかに見渡して、なで島、竹生島などいう所が見えるのは、たいへん趣深い。勢多の橋はみな崩れていて、渡るのが大変だった。
粟津にとどまって、師走の二日、京に入る。暗くなってから行き着こうと、申の時(午後四時)ごろ出発して行くと、逢坂の関近くなって、山腹に仮づくりの「きりかけ」という囲いをしたものの上から、丈六の仏のいまだ粗造りでいらっしゃるのが、顔だけ出ているのが見やられた。
人里はなれてこんな場所にありながら、場所のことなど少しも頓着なさっていないご様子なのが、いかにもありがたい仏さまだなあと、遠くにながめて過ぎた。
多くの国々を通り過ぎてきたが、駿河の清見が関と、逢坂の関だけは、他に比べようもなく素晴らしい。たいそう暗くなってから三条の宮の西にあるわが家に到着した。
前の章「遠江から三河へ」|次の章「物語への憧れ 継母との別れ」