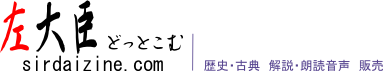長恨歌、姉の不吉な言葉、火事の事
原文
世の中に長恨歌といふふみを、物語に書きてあるところあんなりと聞くに、いみじくゆかしけれど、えいひよらぬに、さるべきたよりを尋ねて、七月七日いひやる。
契りけむ昔の今日のゆかしさにあまの川波うち出でつるかな
返し、
たちいづる天の川辺のゆかしさにつねはゆゆしきことも忘れぬ
その十三日の夜、月いみじく隈なく明きに、みな人も寝たる夜中ばかりに、縁に出でゐて、姉なる人、空をつくづくとながめて、「ただ今ゆくへなく飛びうせなばいかが思ふべき」と問ふに、なまおそろしと思へるけしきを見て、ことごとにいひなして笑ひなどして聞けば、かたはらなる所に、さきおふ車とまりて、「荻の葉、荻の葉」と呼ばすれど答へざなり。呼びわづらひて、笛をいとをかしく吹きすまして、過ぎぬなり。
笛の音のただ秋風と聞こゆるになど荻の葉のそよとこたへぬ
といひたれば、げにとて、
荻の葉のこたふるまでも吹きよらでただに過ぎぬる笛の音ぞ憂き
かやうに明くるまでながめあかいて、夜明けてぞなみ人寝ぬる。
そのかへる年、四月の夜中ばかりに火の事ありて、大納言殿の姫君と思ひかしづきし猫もやけぬ。「大納言殿の姫君」と呼びしかば、聞き知り顔に鳴きて歩み来などせしかば、父(てて)なりし人も「めづらかにあはれなることなり。大納言に申さむ」などありしほどに、いみじうあはれにくちをしくおぼゆ。ひろびろともの深き、み山のやうにはありながら、花紅葉のをりは、四方(よも)の山辺も何ならぬを見ならひたるに、たとしへなくせばき所の、庭のほどもなく、木などもなきに、いと心憂きに、向かひなる所に、梅、紅梅など咲きみだれて、風につけて、かかえ来るにつけても、住みなれしふるさとかぎりなく思ひ出でらる。
匂ひくる隣の風を身にしめてありし軒端の梅ぞこひしき
語句
■長恨歌 玄宗皇帝と楊貴妃の悲恋を描いた中唐の詩人白居による長詩。平安貴族の間で広く愛唱された。玄宗皇帝は楊貴妃を溺愛し、それがもとで国が乱れ安禄山の乱を招く。戦乱の中、玄宗皇帝はやむなく楊貴妃を殺させるほかなかった。乱の終結後、悲しみにたえない玄宗皇帝は道士に訴える。道士は部下の修験者に命じて楊貴妃の魂を探させると、仙人の山の上に太真となのっていた楊貴妃の魂を見出す。修験者は玄宗皇帝の心を伝え、形見の品を持ち帰る。 ■ふみ 漢詩。 ■物語 『長恨歌』の内容を物語風に書いたものか。 ■あるところあんなり 持っている人があるということ ■えひいよらぬ 貸してほしいとお願いすることが、遠慮される。 ■七月七日 『長恨歌』の末尾に「七月七日長生殿 天に在りては願はくは比翼の鳥と作(な)り 地に在りては願はくは連理の枝と為らむと」による。 ■ゆゆしきこと 不吉なこと。楊貴妃は殺され玄宗皇帝は失脚するという不吉な内容であるため、ふだんは人に貸すのをはばかっていたもの。 ■なまおそろし 何となく恐ろしい。 ■ことごとに 別の話題に。 ■さきおふ車 車の先払いをさせている。貴人の車が通るとき、通行人に道をゆずらせた。 ■答へざなり 答えないようだ。「ざ」は打消しの助動詞「ざる」の擬音化(ざん)の無表記。「なり」は推定の助動詞。 ■秋風と… 「秋風」に「秋風楽」が掛けてある。「秋風楽」は雅楽の演目。 ■ながめあかいて 「ながめ」はぼんやりと物思いに沈む。「花の色はうつりにけりないたずらに我が身よにふるながめせしまに」(小野小町) ■かへる年 治安三年(1023年) ■猫もやけぬ 「も」は並列。言外に家も焼けたことを示す。 ■めづらか 不思議であること。 ■たとしへなく 例えようもなく。 ■梅 単に「梅」という時は白梅を指し、香りが愛でられた。紅梅は見た目を愛でた。 ■かかへくる 自然に香ってくる。「かかへ」は「嗅ぐ」の未然形に自発の助動詞「ゆ」のついたもの。■しめて しみこませて。
現代語訳
世の中に長恨歌という漢詩を物語に書いて持っているところがあると聞いて、たいそう読みたく思うけれど、頼むこともできなかったのだが、しかるべきつてを尋ねて、七月七日歌を書き送ってお願いした。
玄宗皇帝と楊貴妃が契ったという昔の今日の日がどんなだか知りたいばかりに、彦星のわたる川波のように、思い切ってあなたに、貸してほしい旨を打ち明けるのです。
返し、
牽牛と織女がその両岸に立って逢うという天の川の川辺には私も心惹かれております。普段は不吉な書物なので人には貸さないのですが、今日はそんなことも忘れて、お貸しいたしましょう。
同じ年の十三日の夜、月がたいそう隈なく明るい晩に、みな人も寝てしまった夜中ごろ、縁側に出て、姉である人が、空をつくづくと眺めて、「たった今私が理由もなく飛び失せてしまったら、あなたはどう思う」と尋ねるのに、なんとなく恐ろしく思っている私の様子を見て、姉は、別の話題にとりつくろって、笑いなどして聞いていると、かたわらの家の前に先払いをしながら進んできた車がとまって、「荻の葉、荻の葉」と呼ばせるが、答えないようだ。
車の主は呼びあぐねて、笛をたいそう優雅に吹きすまして、過ぎていったのだった。
笛の音が、まさしく雅楽の秋風楽と聞こえていたのに、どうして荻の葉はそよとも答えなかったのでしょう。
といったところ、姉はいかにもといって、
荻の葉が答えるまで笛を吹き続けないでそのまま通り過ぎてしまった笛の音の惜しいこと。
このように夜が明けるまでぼんやり物思いに沈んで秋の夜空をながめ、夜が明けてからみな人は寝た。
その翌年、四月の夜中ごろ火事があって、大納言殿の姫君と思ってかわいがっていた猫も焼けてしまった。「大納言殿の姫君」と呼ぶと、その言葉を聞き知っているような顔で歩み来たりしていたので、父である人も「不思議にあはれなことだ。大納言殿のご報告しよう」など言っていたところだったので、たいそうしみじみ悲しく、惜しいことに思われた。
かつての住まいは広々として、人里離れたみ山のようではあったが、桜や紅葉の折には四方の山辺も問題にならないほど素晴らしかった。
それを見慣れていたので、新しい住まいのたとえようも無くせまい所の、庭というほどの広さもなく、木などもないので、たいそう憂鬱で、向いにある家には、白梅・紅梅が咲き乱れて、風がふくと自然と梅の香が香ってくるのにつけても、住み慣れたかつての住まいが限りなく思い出されるのだった。