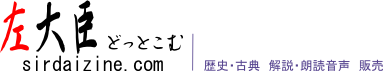乳母の死 源氏物語に読みふける
原文
その春、世の中いみじう騒がしうて、松里の渡りの月かげあはれに見し乳母(めのと)も、三月ついたちに亡くなりぬ。
せむかたなく思ひ嘆くに、物語のゆかしさもおぼえずなりぬ。いみじく泣きくらして見いだしたれば、夕日のいとはなやかにさしたるに、桜の花のこりなく散りみだる。
散る花もまた来む春は見もやせむやがて別れし人ぞこひしき
また聞けば、侍従の大納言の御むすめ亡くなりたまひぬなり。殿の中将のおぼし嘆くなるさま、わがものの悲しきをりなれば、いみじくあはれなりと聞く。
上(のぼ)り着きたりし時、「これ手本にせよ」とて、この姫君の御手をとらせたりしを、「さよふけてねざめざりせば」など書きて、「鳥辺山たにに煙のもえ立たばはかなく見えしわれと知らなむ」と、いひ知らずをかしげに、めでたく書きたまへるを見て、いとど涙を添へまさる。
かくのみ思ひくんじたるを、心もなぐさめむと、心苦しがりて、母、物語などもとめて見せたまふに、げにおのづからなぐさみゆく。
紫のゆかりを見て、つづきの見まほしくおぼゆれど、人かたらひなどもえせず。たれもいまだ都なれぬほどにてえ見つけず。いみじく心もとなく、ゆかしくおぼゆるままに、「この源氏の物語、一の巻よりしてみな見せたまへ」と心のうちにいのる。
親の太秦にこもりたまへるにも、ことごとなくこのことを申して、出でむままにこの物語見はてむと思へど見えず。いとくちをしく思ひ嘆かるるに、をばなる人の田舎より上りたる所にわたいたれば、「いとうつくしう生(お)ひなりにけり」など、あはれがり、めづらしがりて、かへるに、「何をかたてまつらむ。まめまめしき物は、まさなかりなむ。
ゆかしくたまふなる物をたてまつらむ」とて、源氏の五十余巻、櫃に入りながら、在中将、とほぎみ、せり河、しらら、あさうづなどいふ物語ども、一ふくろとり入れて、得てかへる心地のうれしさぞいみじきや。
はしるはしるわづかに見つつ、心も得ず心もとなく思ふ源氏を、一の巻よりして、人もまじらず、几帳のうちにうち臥して引き出でつつ見る心地、后の位も何にかはせむ。
昼は日ぐらし、夜は目のさめたるかぎり、灯を近くともして、これを見るよりほかのことなければ、おのづからなどは、そらにおぼえ浮かぶを、いみじきことに思ふに、夢にいと清げなる僧の、黄なる地の袈裟着たるが来て、「法華経五の巻をとく習へ」といふと見れど、人にも語らず。
習はむとも思ひかけず。物語のことをのみ心にしめて、われはこのごろわろきぞかし、さかりにならば、かたちもかぎりなくよく、髪もいみじく長くなりなむ。光の元治の夕顔、宇治の大将の浮舟の女君のやうにこそあらめと思ひける心、まづいとはなくあさまし。
語句
■治安元年(1021年)春から秋にかけての疫病の流行をさす。 ■松里の渡り 千葉県松戸市。2「産後の乳母を見舞う」に登場。 ■月かげ 月の光に照らされた乳母の姿。 ■やがて そのまま。 ■侍従の大納言 藤原行成(972-1028)権大納言に至るが、侍従でいた期間が長いので侍従の大納言とよばれる。その娘は道長の息子長家と結婚した。 ■御むすめ 行成の娘は治安元年三月十九日に没した。『栄花物語』にその死を人々が嘆いた様子が描か
れている。 ■殿の中将 「殿」は大殿藤原道長。その末子長家が行成の娘と結婚した。当時17歳。右近衛中将従三位。 ■さよふけて 「小夜ふけてねざめざりせば時鳥(ほととぎす)人づてにこそ聞くべかりけれ」(『拾遺集』夏・壬生忠見)詞書に「天暦の御時の歌合に」。 ■鳥辺山… 『拾遺集』哀傷。鳥辺山は京都市東山区。昔の火葬場の跡がこのあたり一帯にあった。 ■思ひくんず 屈す→くんず。思い悩んで、ふさぎこむこと。 ■紫のゆかり 『源氏物語』のうち紫の上に関係するところ。あるいは「若紫巻」。 ■人かたらひ 人に相談すること。 ■太秦 京都市右京区太秦の広隆寺。帰化人系の氏族である秦氏の氏寺で平安京遷都以前からあった平安京最古の寺院。 ■ことごとなく 異事なく ■出むままに 寺を出るとすぐ。 ■をばなる人 不明。菅原孝標女の叔母といえば右大将道綱母が有名だが、すでに995年に亡くなっている。 ■生ひなり 成人すること。 ■まめまめしき物 実用向きのもの。 ■まさなし よくない。ふさわしくない。 ■ゆかしくしたまふなる物 読みたいとおっしゃっているという物。「ゆかし」は~したい。 ■在中将 在原業平を主人公とする『伊勢物語』のこと。 ■とほぎみ 以下、せり河、しらら、あさうづは物語の題名だが実在せず、内容は不明。 ■はしるはしる 飛び飛びに。 ■几帳 T字型の木組みに絹などをかけてついたてにしたもの。 ■おのづからなどは 意味不明。自然にという意味か。 ■そらに 暗誦して言葉が自然に浮かんでくること。 ■法華経五の巻 『法華経』五の巻には女人成仏が書かれている。 ■夕顔 『源氏物語』夕顔巻に登場。恋人頭中将に愛された後、源氏の君のもとに召されるが、六条御息所の生霊に取り殺された。 ■宇治の大将 『源氏物語』宇治十帖の主人公薫。源氏の君の妻・女三の宮と柏木との間にできた不倫の子。 ■浮舟 『源氏物語』宇治十帖のヒロイン。八の宮と侍従中納言の間にうまれ常陸で成長した。後、薫の恋人となるが、匂宮との三角関係に悩んだあげく宇治川に身を投げるが助けられて出家する。
現代語訳
その春、世の中は疫病の流行でたいへんなことである中に、上総の松里の渡で月の光に美しく照らされていたのを見た、あの乳母も、三月一日に亡くなった。どうしようもなく思い嘆いて、物語を読みたいとも思わなくなった。たいそう泣いてばかりいて、外を眺めていると、夕日がたいそう華やかに差しているところに、桜の花がもう枝には残ったものはなく、散り乱れている。
散る花も、また来年の春は美しい姿を見せてくれるというのに、あのまま別れた乳母とは二度と会うことができない。ひどく恋しい。
また聞けば、侍従の大納言藤原行成さまの姫君もお亡くなりになったそうだ。姫とご結婚なさっていた中将殿のお嘆きになる様子は、私自身悲しい折でもあり、たいそうしみじみと共感して、耳にした。
上京した当時、「これを手本にしなさい」といって、この姫君の手蹟をくださったのだが、「さよふけてねざめざりせば」と拾遺集の歌など書いて、「鳥辺山の谷に煙が燃えたっていると、私は死んでしまうのではないかと思う」と、なんとも趣深く、美しい字でお書きになったのを見て、たいそう涙があふれて止まらなかった。
このように思い悩みふさぎこんでばかりいると、私の心を慰めようとして、心配して、母が物語など求めて見せてくださったところ、まったく母の思惑通りだ。自然と慰められていった。
『源氏物語』の紫の上に関係した部分を見て、続きを見たく思うけれど、人に相談もできない。誰れもいまだに都馴れしていない頃だから、物語など見つけてくれようもない。
たいそうもどかしく、読みたいと思うままに、「この源氏の物語、一の巻から全部見せてください」と心の内に祈る。
親が太秦の広隆寺に参籠なさった時も、外でもないこのことを申し上げて、寺を出るとすぐに『源氏物語』を最後まで見たいと思うが見ることはできない。
たいそう残念に思って嘆いていたところ、叔母である人が田舎から上京して住んでいる所を訪ねていったところ、「たいそう可愛らしく、ご成人なさりましたな」など、しみじみ感心し、珍しがって、帰り際に、「何をさしあげましょうか。実用向きのものは、つまらないです。読みたがっていらっしゃるというものを、差し上げましょう」といって、源氏の物語五十余巻、木箱に入れたまま、『伊勢物語』『とほぎみ』『せり河』『しらら』『あさうづ』などという物語もいっしょに一つの袋に入れてもらって帰る心地のうれしさといったら、最高だった。
飛ばし飛ばし、ちらちらと見ては、今まで思い通りに読むことができず、もどかしく思っていた源氏の物語を、一の巻からはじめて、人に邪魔もされず、几帳のうちに臥して引き出しつつ見る心地は、后の位もこれに比べたら、何だろうか。
昼は一日中、夜は目がさめているかぎり、灯を近くともして、これを見るよりほかのことをしないでいると、自然と、暗誦して覚えていた言葉が浮かんでくるのを、素晴らしいことと思っていると、夢にたいそう清らかな僧で、黄色い地の袈裟を着たのが来て、「法華経の五の巻をすぐに習え」というと見たけれど、人にも言わず、法華経なんて習おうとは思いもかけず、ただ物語のことで心はいっぱいで、私は今は器量が悪いけれど、年頃ともなれば、容貌もどこまでも素敵になり、髪もたいそう長くなるでしょう。
光の源氏の夕顔や、宇治の大将薫の君の恋人、浮舟の女君みたいになるでしょうと思っていた心、今思うとほんとにまあ、たわいもない、あきれ果てたものだった。
前の章「物語への憧れ 継母との別れ」|次の章「わが家の庭 六角堂の遣水の夢」